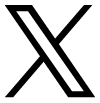◾️2026年の7月のお盆:7月13日(月)~7月16日(木)
7月をお盆の時期とするのは、主に東京都や一部の地域(神奈川、静岡など)で行われるお盆の形式です。「東京盆」と呼ばれることも。
明治時代に政府が新暦(グレゴリオ暦)を導入した際に、旧暦(太陰太陽暦)での7月盆をそのまま新暦に適用したためですが、お盆自体が日本古来の信仰と仏教が融合したような風習だったことから、他の地域には広がりにくかったようです。
◾️2026年の8月のお盆:8月13日(木)~8月16日(日)
全国的に最も一般的なお盆の時期で、多くの企業が「お盆休み」を設けます。旧暦のお盆の時期のため「旧盆」と呼ばれることもあります。
旧盆は、もともと旧暦の7月15日を基準に行われていましたが、新暦に移行した際、旧暦7月15日に近い新暦8月15日に行われるようになりました。地方によっては「月遅れ盆」とも呼ばれます。
◾️お盆休みはいつからいつまで?
2026年のお盆休みは、一般的に 8月13日(木)~8月16日(日)に設定される企業が多いと予想されます。連休を利用して帰省する方も多いでしょう。
更新日: 2025年12月05日
【2026年版】お盆はいつからいつまで?新盆・旧盆の違いや過ごし方を解説!
お盆は、ご先祖様を迎え供養する大切な行事です。しかし、「お盆はいつからいつまで?」「何をすればいいの?」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか?
本記事では、2026年のお盆の時期、新盆・旧盆の違い、お盆の過ごし方を詳しく解説します。また、お盆に必要なアイテムやお供え物のおすすめ商品もご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
2026年のお盆はいつからいつまで?

新盆・旧盆の違いは?
お盆は地域によって時期が異なります。「新暦(グレゴリオ暦)」を基準にしたお盆と、「旧暦」を基準にしたお盆があり、地域ごとの伝統や習慣、農業や漁業の都合などが関係しています。
旧暦の時代からお盆の時期は「7月中旬」だったようですが、明治時代に「新暦」が導入された際、「7月15日」を新暦の7月に合わせた地域と、旧暦の7月(新暦では8月)のままで続けた地域とがあり、結果的に地域によってお盆の時期が異なることになったようです。
地域の風習によってお盆の時期が異なるのは、旧暦が基準だと農業や漁業などの産業の都合で7月よりも8月の方が時間を取りやすいなどの理由から、今でも8月をお盆の時期としている地域が残っています。
旧暦の時代からお盆の時期は「7月中旬」だったようですが、明治時代に「新暦」が導入された際、「7月15日」を新暦の7月に合わせた地域と、旧暦の7月(新暦では8月)のままで続けた地域とがあり、結果的に地域によってお盆の時期が異なることになったようです。
地域の風習によってお盆の時期が異なるのは、旧暦が基準だと農業や漁業などの産業の都合で7月よりも8月の方が時間を取りやすいなどの理由から、今でも8月をお盆の時期としている地域が残っています。
お盆とは?意味や由来を解説

◾️お盆の由来
お盆は、仏教の「盂蘭盆会(うらぼんえ)」に由来し、先祖の霊を迎え供養する行事です。
起源は古代インドの説話で、目連(もくれん)というお釈迦様の弟子が亡き母を救うために僧侶へ供物を捧げたことから始まりました。
この教えが中国、日本へと伝わり、日本では祖先の霊を迎え供養する風習として定着。地域ごとに迎え火や送り火、盆踊りなどの伝統行事が行われます。
◾️なぜお盆に先祖供養をするのか?
お盆は、亡くなった先祖の霊がこの世に帰ってくる時期とされ、家族が集まり供養を行う大切な機会です。
仏教の教えに基づき、先祖への感謝を伝えるとともに、家族の繁栄や無病息災を願う意味もあります。また、お盆の供養を通じて、故人を偲び、命のつながりを再確認する大切な時間とされています。
お盆は、仏教の「盂蘭盆会(うらぼんえ)」に由来し、先祖の霊を迎え供養する行事です。
起源は古代インドの説話で、目連(もくれん)というお釈迦様の弟子が亡き母を救うために僧侶へ供物を捧げたことから始まりました。
この教えが中国、日本へと伝わり、日本では祖先の霊を迎え供養する風習として定着。地域ごとに迎え火や送り火、盆踊りなどの伝統行事が行われます。
◾️なぜお盆に先祖供養をするのか?
お盆は、亡くなった先祖の霊がこの世に帰ってくる時期とされ、家族が集まり供養を行う大切な機会です。
仏教の教えに基づき、先祖への感謝を伝えるとともに、家族の繁栄や無病息災を願う意味もあります。また、お盆の供養を通じて、故人を偲び、命のつながりを再確認する大切な時間とされています。
お盆の過ごし方6選
お盆は先祖供養を中心に、家族と過ごす時間でもあります。以下の6つを実践し、ご先祖様を大切にしましょう。

① 迎え火・送り火を焚く
お盆の始まりには「迎え火(むかえび)」、お盆の終わりには「送り火(おくりび)」を焚きます。
「迎え火」は、ご先祖様の霊が迷わず帰ってこられるようにとの目印で、「送り火」は、お盆が終わる際にご先祖様の霊をあの世へお送りするための火です。
一般的には、家の門口や玄関先で麻の茎(おがら)を焚きます。地域によっては、京都の「五山の送り火」のような大規模な行事もあります。
お盆の始まりには「迎え火(むかえび)」、お盆の終わりには「送り火(おくりび)」を焚きます。
「迎え火」は、ご先祖様の霊が迷わず帰ってこられるようにとの目印で、「送り火」は、お盆が終わる際にご先祖様の霊をあの世へお送りするための火です。
一般的には、家の門口や玄関先で麻の茎(おがら)を焚きます。地域によっては、京都の「五山の送り火」のような大規模な行事もあります。

② お墓参り
お盆には、ご先祖様を迎えるためにお墓参りを行い、お墓を掃除し、線香や花を供え、手を合わせて感謝の気持ちを伝えます。
最近では、遠方のためにお盆時期のお墓参りが難しい場合、オンライン墓参りや代行サービスを利用する人も増えています。
お盆には、ご先祖様を迎えるためにお墓参りを行い、お墓を掃除し、線香や花を供え、手を合わせて感謝の気持ちを伝えます。
最近では、遠方のためにお盆時期のお墓参りが難しい場合、オンライン墓参りや代行サービスを利用する人も増えています。

③ お盆のお供えをする
お盆には、ご先祖様が迷わず家に帰れるよう、仏壇や精霊棚を飾り、お供え物をします。
代表的なものとして、故人の好物や果物、そうめん、団子などがあります。
「精霊馬(しょうりょううま)」と呼ばれるキュウリの馬とナスの牛を作る地域も多く、これには「ご先祖様が馬で早く来て、牛でゆっくり帰ってほしい」という願いが込められています。
お盆には、ご先祖様が迷わず家に帰れるよう、仏壇や精霊棚を飾り、お供え物をします。
代表的なものとして、故人の好物や果物、そうめん、団子などがあります。
「精霊馬(しょうりょううま)」と呼ばれるキュウリの馬とナスの牛を作る地域も多く、これには「ご先祖様が馬で早く来て、牛でゆっくり帰ってほしい」という願いが込められています。

④ 精進料理を食べる
お盆には肉や魚を使わない精進料理を食べる習慣があります。これは仏教の教えに基づき、ご先祖様への供養の一環とされています。
代表的な料理には、高野豆腐、煮しめ、胡麻豆腐などがあります。
精進料理は素材の味を生かし、感謝の気持ちを持ちながら食事をすることで、ご先祖様とのつながりを改めて感じさせてくれます。
お盆には肉や魚を使わない精進料理を食べる習慣があります。これは仏教の教えに基づき、ご先祖様への供養の一環とされています。
代表的な料理には、高野豆腐、煮しめ、胡麻豆腐などがあります。
精進料理は素材の味を生かし、感謝の気持ちを持ちながら食事をすることで、ご先祖様とのつながりを改めて感じさせてくれます。

⑤ 盆踊りに参加する
盆踊りは、お盆に帰ってきたご先祖様の霊を供養し、送り出すための伝統行事です。
全国各地で様々な盆踊りが開催され、有名なものに「阿波踊り」や「郡上おどり」などがあります。
浴衣を着て輪になって踊ることで、地域の人々との交流を深める場にもなります。
音楽や太鼓の音に包まれながら、先祖への感謝とともに夏の風情を楽しむことができます。
盆踊りは、お盆に帰ってきたご先祖様の霊を供養し、送り出すための伝統行事です。
全国各地で様々な盆踊りが開催され、有名なものに「阿波踊り」や「郡上おどり」などがあります。
浴衣を着て輪になって踊ることで、地域の人々との交流を深める場にもなります。
音楽や太鼓の音に包まれながら、先祖への感謝とともに夏の風情を楽しむことができます。

⑥ 家族とゆっくり過ごす
お盆は、普段忙しく過ごしている人々にとって、家族と過ごす貴重な機会です。
親戚が集まり、思い出話をしたり、食事を共にすることで、家族の絆を深めることができます。
遠方に住む家族ともオンラインでつながることができる時代ですが、実際に顔を合わせて過ごす時間は、特別なものです。ご先祖様を偲びながら、心温まる時間を大切にしましょう。
お盆は、普段忙しく過ごしている人々にとって、家族と過ごす貴重な機会です。
親戚が集まり、思い出話をしたり、食事を共にすることで、家族の絆を深めることができます。
遠方に住む家族ともオンラインでつながることができる時代ですが、実際に顔を合わせて過ごす時間は、特別なものです。ご先祖様を偲びながら、心温まる時間を大切にしましょう。
お盆に必要なものと通販で買えるおすすめ商品
お盆を迎えるにあたり、事前に準備しておきたいアイテムをご紹介します。

出典:https://shopping.jreast.co.jp/products/detail/s248/s248-4902064163034
① 迎え火・送り火セット
迎え火・送り火を行うためには、「おがら(麻の茎)」「火皿(素焼きの皿)」やマッチ・ライターが必要です。
おがらは火がつきやすく、清浄な植物とされ、仏壇用のセットとしても販売されています。
迎え火・送り火を行うためには、「おがら(麻の茎)」「火皿(素焼きの皿)」やマッチ・ライターが必要です。
おがらは火がつきやすく、清浄な植物とされ、仏壇用のセットとしても販売されています。

出典:https://shopping.jreast.co.jp/products/detail/s299/s299-4902125371064
② お線香
お盆のお参りや仏壇での供養には、お線香が欠かせません。
線香の香りには、心を落ち着かせる効果があり、ご先祖様の霊を迎える際の清めの意味も持ちます。
長時間燃えるものや煙が少ないタイプなど、さまざまな種類があり、故人の好みに合わせた香りを選ぶことも供養の一つです。
お盆のお参りや仏壇での供養には、お線香が欠かせません。
線香の香りには、心を落ち着かせる効果があり、ご先祖様の霊を迎える際の清めの意味も持ちます。
長時間燃えるものや煙が少ないタイプなど、さまざまな種類があり、故人の好みに合わせた香りを選ぶことも供養の一つです。

出典:https://shopping.jreast.co.jp/products/detail/s050/s050-osonaem-a
③ お供え用の生花
お盆には、仏壇やお墓に新鮮な生花を供えます。枯れにくく、香りが強すぎず、棘がないお花が良いとされており、定番の花として、菊やリンドウ、カーネーションなどがあります。
これらの花は長持ちし、故人を偲ぶ清らかな印象を与えます。地域によって花の種類や飾り方に違いがあり、故人が好きだった花を供えることも心のこもった供養となります。
お盆には、仏壇やお墓に新鮮な生花を供えます。枯れにくく、香りが強すぎず、棘がないお花が良いとされており、定番の花として、菊やリンドウ、カーネーションなどがあります。
これらの花は長持ちし、故人を偲ぶ清らかな印象を与えます。地域によって花の種類や飾り方に違いがあり、故人が好きだった花を供えることも心のこもった供養となります。

④ 精進料理セット
お盆では、ご先祖様への供養として精進料理を用意します。肉や魚を使わず、野菜や豆類を中心とした料理で、代表的なものに煮しめ、高野豆腐、胡麻豆腐などがあります。素材の味を生かし、感謝の気持ちを込めていただくことが大切です。家庭によっては、お膳を整えて仏前に供えることもあります。
お盆では、ご先祖様への供養として精進料理を用意します。肉や魚を使わず、野菜や豆類を中心とした料理で、代表的なものに煮しめ、高野豆腐、胡麻豆腐などがあります。素材の味を生かし、感謝の気持ちを込めていただくことが大切です。家庭によっては、お膳を整えて仏前に供えることもあります。

⑤ 果物・和菓子の詰め合わせ
お盆のお供え物として、季節の果物や和菓子が選ばれます。
果物では、桃、梨、ブドウなどが人気で、仏壇に彩りを添えます。和菓子では、おはぎや落雁が定番で、ご先祖様への感謝を表すとともに、家族や親戚が集まった際のおもてなしにもなります。供えた後に皆で分け合って食べることで、故人を偲ぶ機会にもなります。
お盆のお供え物として、季節の果物や和菓子が選ばれます。
果物では、桃、梨、ブドウなどが人気で、仏壇に彩りを添えます。和菓子では、おはぎや落雁が定番で、ご先祖様への感謝を表すとともに、家族や親戚が集まった際のおもてなしにもなります。供えた後に皆で分け合って食べることで、故人を偲ぶ機会にもなります。
新盆とは?特別な供養の方法

「新盆(にいぼん・しんぼん)」とは、亡くなって四十九日を過ぎた後、初めて迎えるお盆のことです。通常のお盆と比べて、より丁寧な供養を行います。
◾️新盆の供養方法
新盆(初盆)は、故人が亡くなってから初めて迎えるお盆で、特に丁重に供養を行います。
白提灯を飾り、ご先祖様とともに故人の霊を迎えます。僧侶を招いて読経をお願いし、親族や知人が集まり焼香やお供えをして供養します。
精進料理や故人の好物を供え、思い出を語り合うことも大切です。地域によって風習が異なるため、事前に確認して準備しましょう。
新盆を迎える方は、事前に準備をしておきましょう。
◾️新盆の供養方法
新盆(初盆)は、故人が亡くなってから初めて迎えるお盆で、特に丁重に供養を行います。
白提灯を飾り、ご先祖様とともに故人の霊を迎えます。僧侶を招いて読経をお願いし、親族や知人が集まり焼香やお供えをして供養します。
精進料理や故人の好物を供え、思い出を語り合うことも大切です。地域によって風習が異なるため、事前に確認して準備しましょう。
新盆を迎える方は、事前に準備をしておきましょう。
お盆を大切に過ごし、ご先祖様への感謝を伝えよう
お盆は、ご先祖様を偲び、家族の絆を深める大切な行事です。
迎え火やお墓参り、精進料理や盆踊りなど、地域や家庭ごとの風習を大切にしながら供養を行いましょう。特に新盆を迎える方は、事前の準備をしっかり整えることが大切です。
今年のお盆は、ご先祖様への感謝の気持ちを込めて、心温まるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。
迎え火やお墓参り、精進料理や盆踊りなど、地域や家庭ごとの風習を大切にしながら供養を行いましょう。特に新盆を迎える方は、事前の準備をしっかり整えることが大切です。
今年のお盆は、ご先祖様への感謝の気持ちを込めて、心温まるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。